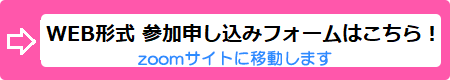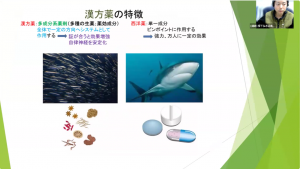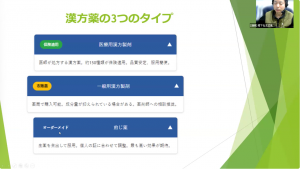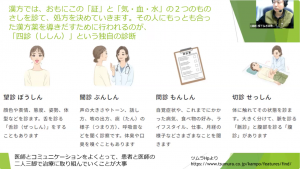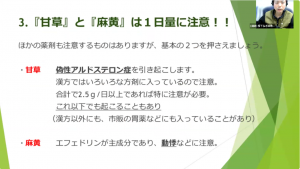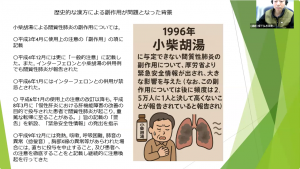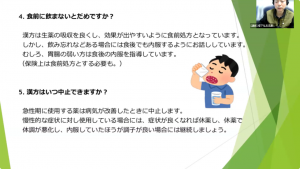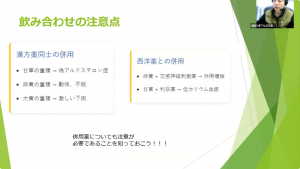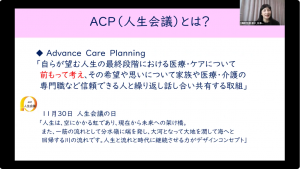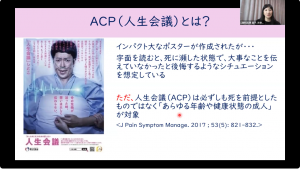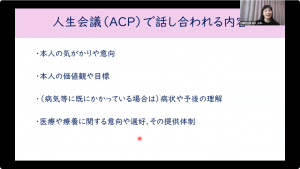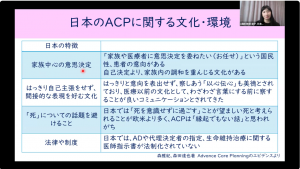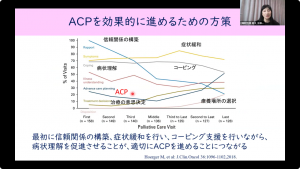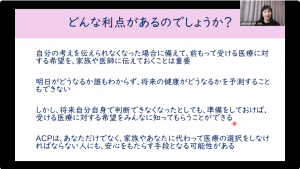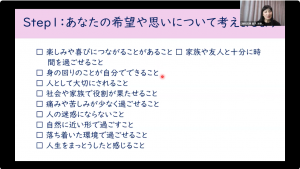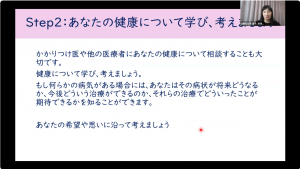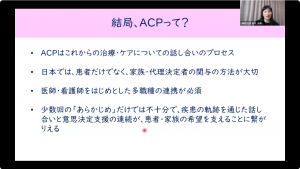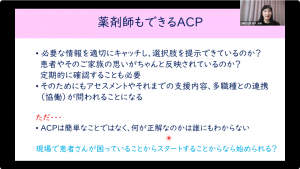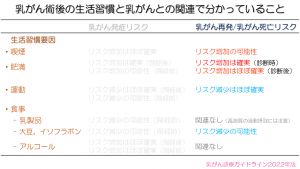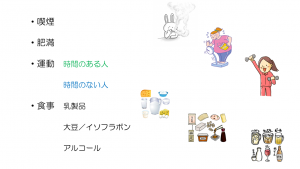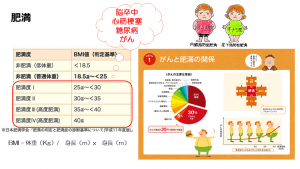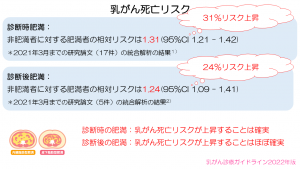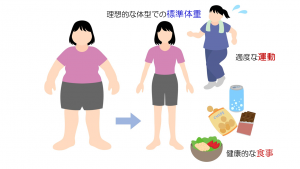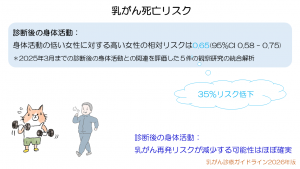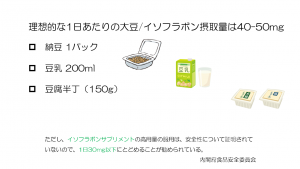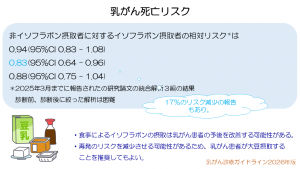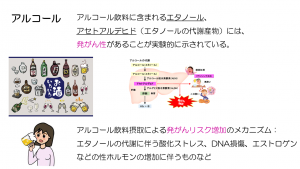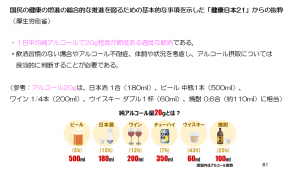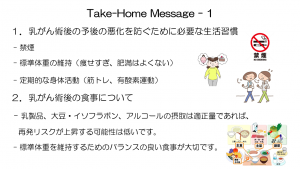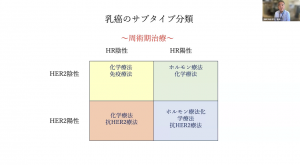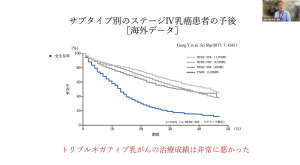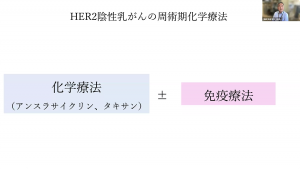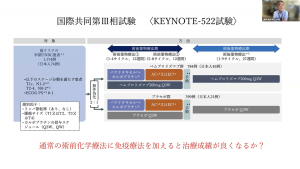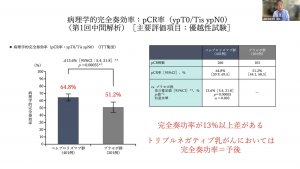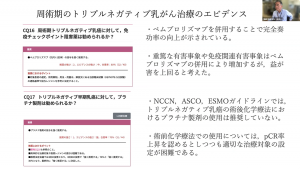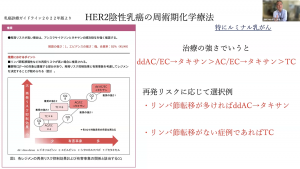第170回まちなかリボンサロンはWEBオンライン形式のみで行います。
レクチャー後に、チャットからの質問コーナーも設けます。
匿名(ニックネーム)で参加できますので、お気軽にご質問ください。
(その場でお答えしますが、時間の都合上全員の質問にお答えできない場合もあります)
また質問コーナー終了後、希望者のみ、そのまま残っていただきオンラインでのおしゃべり会も開催しています。おしゃべり会には、先生方も参加します。
もちろんミニレクチャーの聴講だけの参加でも結構です。
詳しくは、こちら<<< をご覧ください。
<WEBオンライン形式>
パソコンやスマートフォンからzoom(インターネット)を使ってご参加ください。
以下の「申し込みフォームボタン」から事前のzoom参加の登録をお願いします。
定員が100名となっておりますので、お早目にお申し込みください。
サロン参加ルールを設けていますので、必ずお申込み前にご確認ください。
■サロン参加ルール はこちら
日 時:2026年3月7日(土)14:00~16:00
☆ミニレクチャー
『 肩の運動とリンパ浮腫予防 』
講師:広島大学病院 作業療法士 金山 亜希 先生
※申し込みフォームが変わりました。
内容に沿って名前(ニックネームでも可)、メールアドレス等を入力してください。
申し込み直後に、参加URLをお知らせする受付確認メールが「zoom」から届きます。
●必ず所定のお申込みフォームからお願いします。
●参加のURL は、申し込み者ごとで違います。リンクを共有しないでください。
●一人でPC、スマホ、タブレットなどを複数使ってのご参加はご遠慮願います。
●申し込み方法について分からないことがあれば、事務局までメールでお尋ねください。
LINE公式アカウントを始めました。
まちなかリボンサロン申し込み開始のお知らせをする予定です。
https://lin.ee/5vrmi9o